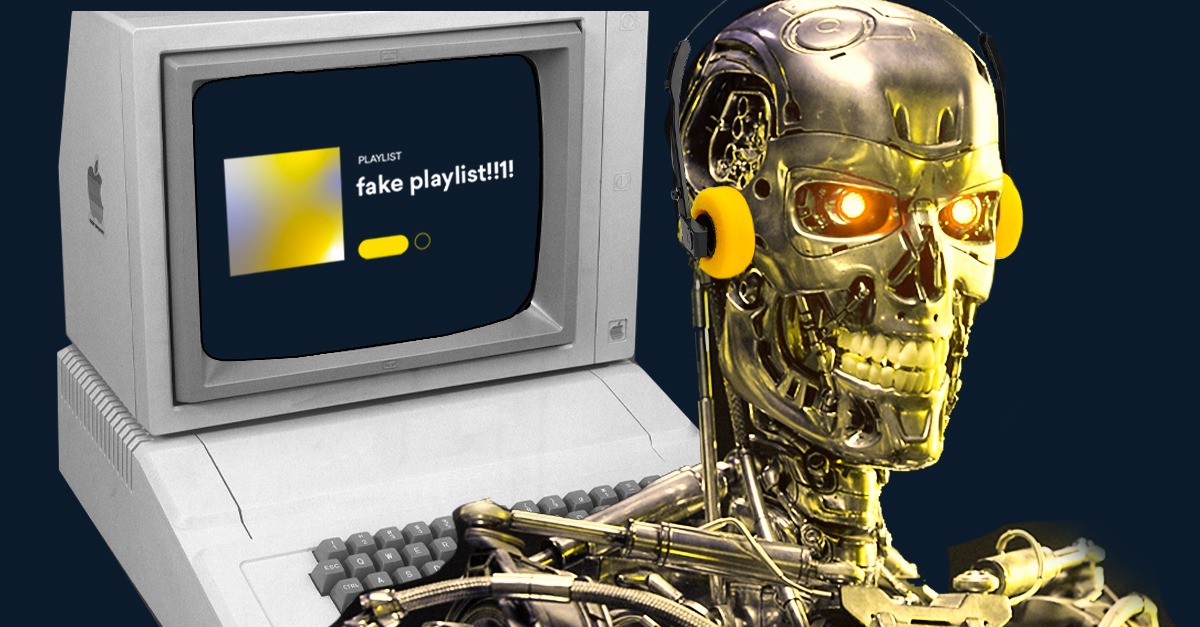音楽の決定的瞬間:シンセの達人10人と彼らが愛した機材たち

アシッドハウスとインドのボリウッド映画に共通項があることを知っていますか?
この記事は読者のコメントにヒントを得て書かれました。読者のディーは、アシッドハウスが生まれる前にTB-303を使っていたチャランジット・シンをチェックするよう提案したのです。
私はシンのことを知らなかったのですが、この発見ですぐにお気に入りになりました。
その週、私は記事に書くMIDIコントローラー選び,のまっただ中だったので、これらの出来事には考えさせられました。
どのようにして1台の機材が特別な音楽家の手に触れたのか?そしてその機材とどのような関係を構築していったのでしょうか?
それでは(ディーの提案も含む)10人のシンセの達人と、彼らのサウンドを形作ったマシンのストーリーを紹介します。
1. ウェンディー・カルロス–Moog modular
現在76歳のウェンディー・カルロスは、全ての電子音楽家達にとって恩恵を与えたパイオニアです。カルロスは、アメリカのコロンビア・プリンストン エレクトロニックミュージックセンター で、最初期の電子音楽の教育を受けました。卒業後、彼女はロバート”ボブ”モーグと出会い、彼が初期に手がけたシンセの改良を手助けしました。彼女の選んだシンセは後に Moog modular となったのです。
「私がMoogを手に入れ、ボブ(・モーグ)と一緒にタッチセンシティブ・キーボードの試作品を手がけたわ。70年代後半まで、大抵の鍵盤はタッチ・センシティブではなかったことが信じられる?だから私は音が生き生きと鳴るような鍵盤にしたのよ。」 ウェンディー・カルロス
彼女を象徴するアルバム Switched on Bach (1968) によって、人々がシンセサイザーという楽器の存在を知るようになりました。 多くの人にとってシンセサイザーが道の楽器だった時代に、カルロスはシンセサイザーでバッハの有名なブランデンベルグ協奏曲の演奏を録音したのです。
「私はバッハを復興させるつもりは特に無かった。ただ愛すべき音楽だから、そしてボブ・モーグの新しいシンセを開発する段階にすごくマッチしたからよ。」 ウェンディー・カルロス
Switched on Bach は、幅広い人々をこの新しいマシン=シンセサイザーのサウンドに夢中にさせた最初のアルバムとなりました。後にクラシック音楽を超える実験としても成功したのです。
2. エリアーヌ・ラディーグ – ARP 2500
エリアーヌ・ラディーグはフランスの電子音響作曲家であり、1950年代にミュージック・コンクレートの作曲家として著名だった、ピエール・シェフェールとピエール・ヘンリーに師事しました。彼女は1960年代にニューヨークを訪問中、ジョン・ケージやフィリップ・グラス、スティーブ・ライヒといったアバンギャルド音楽のシーンに出会います。彼女のスタイルはコンクレートの伝統的手法から遠ざかり、テープを使ったループやマイクのフィードバック・徐々に展開していくモジュレーションといった実験に傾倒していきます。
「ラディーグの作品では、サウンドが生物の細胞がお互いに反応しあうように、グリッサンドを極端に遅くしてすごくゆっくり進行するものだった。」ジュリアン・ベッケール
1970年代に入り、彼女はニューヨークに戻りローリー・スピーゲルとスタジオを構えました。そこで彼女はBuchlaやEML Electro comp といった様々なシンセサイザーで実験を始めた。 しかし彼女にとってぴったりはまったのは ARP 2500でした…。
「…ARPはすぐに私の所にあるオシレーターから目を通すよう依頼してきた。スイッチにノイズを出す欠陥があることを除けばちゃんとしていたわ。でも私にとってはその欠陥こそがサウンドに豊かさと揺らぎをを与えていた。モーグとブックラは素晴らしい楽器だけど、逆にそれらはクリアで金属的な鳴りだった。」ー エリアーヌ・ラディーグ
ラディーグは最終的にチベット仏教に出会い、自身の哲学として帰依します。それは、彼女の最もよく知られた作品 Trilogie de la Mort (1988-1993) に繋がる考え方となります。 ここ十数年で彼女はアコースティックな楽器に傾倒していきますが、その前に電子音楽で残した最後の作品は L’île Re-sonante (2000) でした。
3. クラウス・シュルツ – EMS Synthi A
シュルツがシンセを選んだのは70年代初頭。彼はタンジェリンドリームと、コズミックロックバンドのアシュ・ラ・テンペルの初期メンバーでした。 電子音の実験を進めていったのは彼のソロしてのキャリアでした。彼は自分名義で40枚以上のスタジオ録音のアルバムを発表。 EMS Synthi A は彼にとって最初のシンセであり、もっとも愛したシンセでもありました。
「私にとってEMS Synthi Aは空気感を創り出すシンセで、世界中の他のシンセではできないことなんだ。」– クラウス・シュルツ
彼はその後Big Moogとシーケンサーを導入しました。 彼のwebサイトにある 機材リストには仰天させられます。こんにち、クラウス・シュルツは、ドイツの北西部にある森に小さなスタジオを構え、妻と共に暮らしています。長い年月の末、彼は沢山の機材を手放してしまいました。しかし、EMS Synthi Aは常に彼のコレクションの中に残っています。
…Big Moogはもうない。クラウスがもう使わないからと売ってしまったのだ。 この楽器は彼の音楽の特徴だっただけに、多くの人々は本当に残念がった。とはいえ、クラウスにとっては、そのMoogも楽器すなわち便利な道具以外の何物でも無かった。」–ミスター・モジュラー
現在シュルツは音楽制作に VSTプラグイン と DAW を使っています。(ほら、シンセの達人ですらアナログ原理主義ではないのですよ!)
4. スザンヌ・シアニ – Buchla
スザンヌ・シアニのポートフォリオは、少なく見積もっても記憶に残るものです。 それは 1980年代のゼノン・ピンボール・マシンに使われた効果音。 気の毒なまでにポップなコカ・コーラのコマーシャルや、GEが最初に発売した 音の出る食器洗い機 … これのサウンドは全てスザンヌによるものです。ヤマハDX7 のファンは、彼女が”East Meets West”のプリセットを作ったことを知れば嬉しいしょう。彼女が作曲やサウンドデザインに好んで使うシンセは、常に Buchlaでした。シアニの楽器に対する哲学は、その機材の持つ文脈にアプローチすることなのです。
「こういうことがしたい、というプリセットされた考えで、[Buchla] に触れるべきではないでしょうーこの機材と共鳴することで、自分の伝えたいことを高めていく機材なのです。」-スザンヌ・シアニ
Moogのシンセとは違い、Buchlaのモジュラーの入力装置は鍵盤を中心としたものではありません。主にノブやパッチケーブルによって入力するのです。
「私は、人々がバイオリンを演奏する技法と同じような感じで、Buchlaでの演奏技法を開発したかった…ドン・ブックラは、Buchlaをパフォーマンス向けの楽器として考えていて、私は彼のやり方を信じたわ。だから私はBuchlaならではのパフォーマンスをしたかったの。」–スザンヌ・シアニ
シアニは、しばらくBuchlaに向かい、またピアノに戻りました。しかし、近年再発された彼女の初期作品(1975年の”ブックラ・コンサート”のような)は、電子音に対する彼女の情熱を再びかき立てました。スザンヌ・シアニはMoogfest 2016(訳注:
5. マイケル・スターンズ – Serge synthesizer
マイケル・スターンズの名前を聞いてもすぐにはピンとこないかも知れませんが、彼の音楽を耳にしたことはあるはずです。彼はロン・フリッケの印象的なIMAX映画クロノス、バラカ、サムサラのサウンドトラックを手がけました。彼の音楽に対するアプローチは、ニューエイジの精神性に基づくものです。
「音楽は、自分自身の個性や文化・人種といった「物語」を伝えるものである。私たちはこれらの「物語」を通して、自分たちの生活や、世代を通して語り継がれてきた無意識下の様式を絶えず再構築している。」– マイケル・スターンズ
スターンズの友人であるケビン・ブラエニーは、Sergeのモジュラーシンセ の初期デザインチームにいました。 このシンセを産み出したサージ・チェレプニンは、Buchlaのモジュラーのようなシンセを作りたかったものの、それは真似できない物であり高価なものだったのです。1970年代、ブラエニーがスターンズにSergeシンセを見せると、彼はすぐに気に入りました。
スターンズは自分のSergeを組む前に、Sergeで1979年のアンビエントアルバムMorning Jewelの録音をしました。
5. ローリー・シュピーゲル – Buchla, Music Mouse
ローリー・シュピーゲルは、60年代後半にアナログシンセの虜になりました。
ミカエル(チャイコフスキー:作曲家)に書いていた曲の断片を見せたら、彼は’君はこれに興味を持つと思うよ’と言ったわ。そして彼は私をモートン・サボットニックのスタジオに連れて行って、私にBuchlaのシンセサイザーを見せてくれたの。」– ローリー・シュピーゲル
1970年代、彼女はベル研究所 でコンピューターで対話型の作曲ソフトウェアを開発する仕事をしていました。彼女と同僚のマックス・マシューズは、コンピューター・ミュージックのパイオニアとして尊敬されるようになります。ベル研究所はシュピーゲルに、最初のデジタル加算合成シンセサイザーであるアレス・シンセ のような試験的な機材に接する機会を与えました。シュピーゲルはアレス・シンセを見事に弾きこなしています:
1985年に彼女は代表作であるMusic Mouseというソフトウェアを書き、コンピューターをベースにした楽器の初期のお手本となりました。シュピーゲルにとって、コンピューターは新しい形の伝統音楽の一種だったのです。それは先進性があるアイデアであり、おそらく現在そうなったようにコンピューターがベッドルームでの制作に使われるであろうという先見の明でした。近年、シュピーゲルの作品は1980年にGROOVE systemで作られたThe Expanding Universeなどが再プレスされて注目を集めています。
6. チャランジット・シン – TB-303
シンは、1970年代から80年代にかけて数々のボリウッド映画のサウンドトラックを手がけた、インド人の作曲家/セッションミュージシャンです。彼は1982年のアルバムSynthesizing: Ten Ragas to a Disco Beat により、アシッドハウスを「偶然に」 発明したという評価を得ます。このレコードは、インドの伝統的なラーガと電子音のディスコを融合させたものでした。この作品はインドでリリースされた当初、商業的には失敗した作品でした。しかし、2010年に再発された時はヒット作品となります。シンはアルバムの制作に、シンセサイザーのJupiter-8・TR-808・TB-303という3台のRoland製品を使いました。この303が発売されたのは、Ten Ragasが出るたった1年前。 シンはこれをシンガポールで購入し、自宅でいじくり倒しました。彼は「いい音だ、これを録音しない手は無い」と思いました。ピキピキいうベースラインは、後にアシッドハウスとして定義されましたが、シンはそのアシッドハウスが影も形も無い頃にやっていたのです。
「TB-303は当初ベースギターの役割を果たすために設計されたが、従来のベースラインを表現するには使いづらかったので、シンは違う使い方を発見し、中でもハマったのがインドのラーガ音楽の旋律を表現するのに最適なグリッサンド機能だった。」– The Wire
8. ヴァンゲリス – Yamaha CS80
ギリシャ生まれのヴァンゲリスは、映画炎のランナー(1981)やブレードランナー(1982)のサウンドトラックが、数多くの作品の中でも代表作になっています。1960年代と70年代、ヴァンゲリスはいくつかのバンドで演奏し、特にアフロディテス・チャイルドでのキーボードが有名です:
ヴァンゲリスはシンセサイザーを「シンフォニック・エレクトロニカ」として名付けたスタイルで使っていました。旋律はシンプルでありながらも、伝統音楽の面影がある印象に残る進行です。ヴァンゲリスと彼を象徴するYamaha CS80シンセの関係は興味深い物です。
(CS80は)私のキャリアの中でもっとも重要なシンセサイザーであり、私にとってこれまでのアナログシンセサイザーの中で最高のデザインだ。私が本物の楽器と呼べる唯一のシンセサイザーで、それは主に鍵盤によるものだーそれはこのシンセが作られ、演奏できる所以である。」–ヴァンゲリス
YAMAHA CS80は日本初の偉大なシンセサイザーとして受け入れられました。ピアノのようなウェイテッド鍵盤とポリフォニックのアフタータッチを持つ、表現力豊かなポリ・シンセサイザーです。ヴァンゲリスはYAMAHA CS80の演奏を自分を象徴するスタイルに発展させました。彼は鍵盤毎に異なるアフタータッチを加えることで、美しいビブラートのエフェクトを創り出したのです:
9. ドリス・ノートン – Roland System 700, Roland System 100M, Minimoog
イタリア出身のドリス・ノートンは、電子音楽の中でも真に無名のヒーローです。彼女は素晴らしい音楽を作るだけで無く、フリーのジャーナリストでもあり、脚本家でもあり、のちにIBMへの音楽コンサルタントもつとめます。1980年代初頭のシーケンサーとドラムマシンにより作りだされたノートンのリズムは革新的なものでした。彼女はテクノが影も形も無かった頃にテクノを作っていたのです。
「私は音楽キャリアを始めたつもりなど無かった。音楽は私の旅の中の一つでしかない。ADコンバーターやシーケンサーそれからコンピューターや電子機器全般が、自分一人での航海に影響を与えたのよ」–ドリス・ノートン
彼女がMINI MOOGと共にお気に入りだったシンセは、System 700MとSystem 100MというROLAND製の2つのモジュラーでした。彼女はまた、コンピューターを電子楽器として使う初期の提唱者でもありました。
「60年代後半、私は既にコンピューターを「パーソナルなものとして」取り入れていたわ。」–ドリス・ノートン
ノートンのUnder Ground(1980)とPersonal Computer(1984)といった最初のリリースは、アルバムのジャケをみればわかるように、Appleが最初に音楽のスポンサーをした作品です。
10. ケイトリン・オーレリア・スミス–Buchla 100
1987年生まれのスミスは、バークリー音楽院で作曲とサウンドのエンジニアリングを学び始めました。彼女はEver Islesというフォークバンドを結成しました。ところが、近所の人が彼女にBuchla 100 Systemを貸した時、彼女は完全にフォーク・ミュージックを捨て、電子音の世界を選んだのでした。
Buchlaの多彩で予測のつかないサウンドは、スミスが愛した自然で有機的なサウンドに共鳴しました。
「その当時、シンセはほとんどが(ボブ)モーグとブックラでしたが、モーグはよりピアノの言語に翻訳しやすいシンセを作ろうとしていました。でも、ドンはその正反対。彼は鍵盤に慣れ親しんだ頭の中の部分を切り離し、そこにアクセスしやすくなるものを作ろうとしていました。」–ケイトリン・オーレリア・スミス
スミスはアルバムを何枚かリリースし、中でももっとも著名なEARS(2016)は、Buchlaとボーカルをフィーチャーしたものでした。スザンヌ・シアニとケイトリン・オーレリア・スミスは、BuchlaにフォーカスしたSungeryと名付けられたリリースで共作しました。このリリースは ドン・ブックラが逝去するたった数日前の2016年9月15日に発売されました。
機材愛は時間を食う
これらのアーティストに共通する要素は何でしょう?
彼らはみな愛した機材と何時間も向かいあいました。スザンヌ・シアニはこう述べました。「まさに時間が大事で、楽器と向かい合う時間が長ければそれだけ深いところにいけるんだ。」
また、彼らの周りには指導者や似たような考えを持つアーティストのコミュニティーがありました。才能と好奇心には、それを育てる肥沃な土地が必要です。
手先の技能を音楽の創造にまで発展させるには、まず自分に合った正しいツールを見つけることから始めましょう。
選んだツールの可能性や制限・欠点を、逆に自分のサウンドのシグネイチャーにすることで、Moogを選ぶのかコンピューターを選ぶのかの議論になるのです。
LANDRブログの投稿を見逃すことはありません