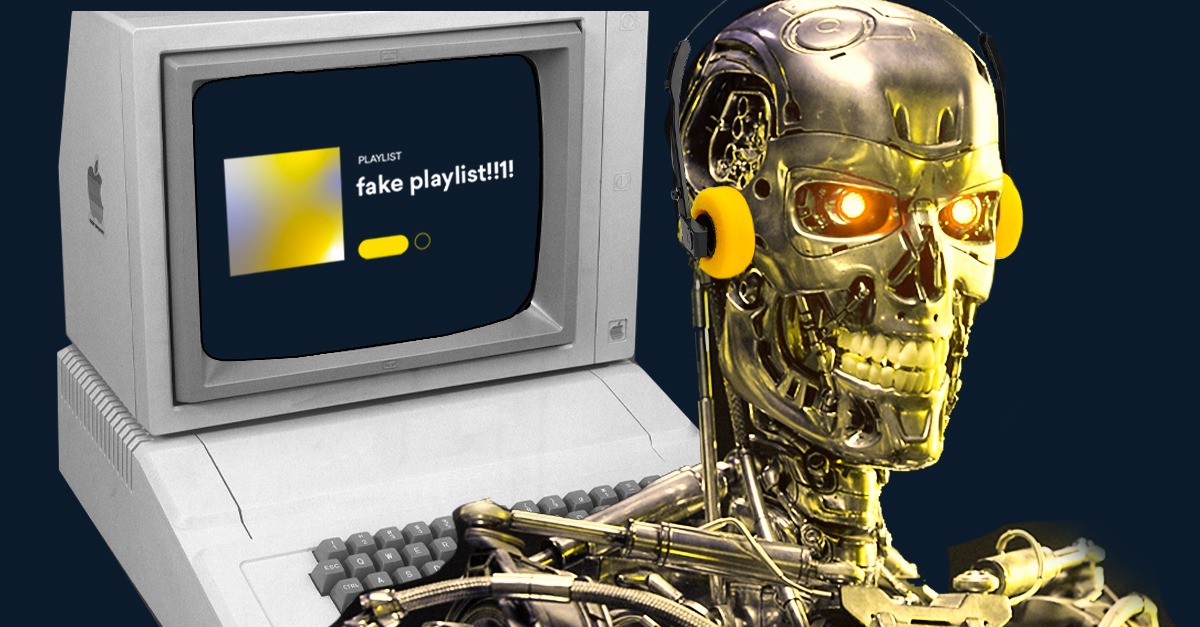7つの抽象的なミックス用語:その意味と使い方
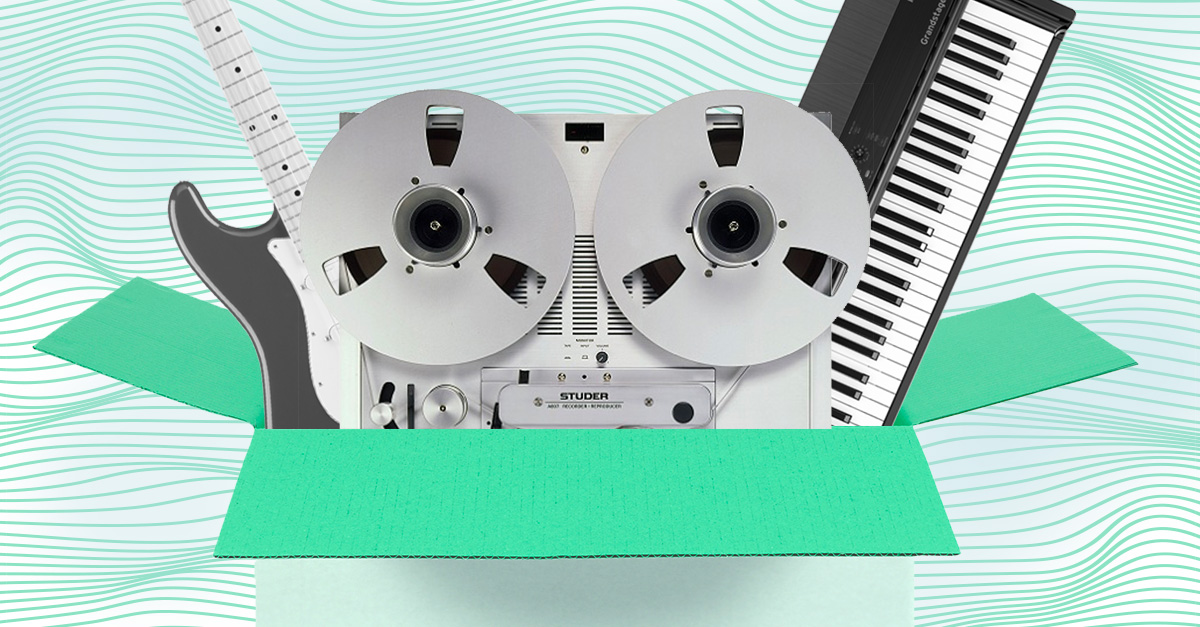
エンジニアは音楽のミックスcについて話し始めると簡単に心に火がついてしまいます。
自分のサウンドを言葉で説明するのは難しいものです。テクニカルな専門用語が飛び交う中で自分のトラックについて説明するのはとてもイライラします。
しかし幸いなことに、ミックスの問題やサウンドクオリティーを説明するのに便利な、共通用語があります。
最も一般的な「不思議な」ミックス用語を7つご紹介します。その意味と、それらのミックス要素を取り扱う方法をお伝えします。
1.「ブーミー」

「ブーミー」とは、スピーカー上で持続している、過度な低周波エネルギーを意味します。
例: 「太いキックが欲しいんだけど、これちょっとブーミーだよね」
「太いキックが欲しいんだけど、これちょっとブーミーだよね」
スピーカーは低域を正確にしか再現できません。
過度な低域はスピーカーを苦しめます。これは周波数スペクトラムにも悪影響として現れます。
解決方法
たくさんの低音を含む音源に対し、ハイパスフィルターを適用してブーミーベースに対応します。
その音の問題点が現れる限界までフィルターを動かしていきます。予想以上にカットできるでしょう。
2.「マディー」

「マディー」は一般的に、競合する中低域要素の積み重ねが詰まりすぎることを意味します。
例: 「ベースのミュートを外すと全体のミックスがマディーになるなあ。250Hzあたりをカットしたほうがいいかもしれない」
中低域の扱いは初心者や中級者には難しいものです。あまりにも「マディー」な状態だと、楽器の明瞭さや分離が影響を受けます。
解決方法:
意図的でない限り、中低域を分けて作り込み、マディーなミックスになることを避けましょう。
キックやベースのような、低域に影響を与える楽器は、真っ先に中低域を調整する対象になります。
これらの音源のほとんどのエネルギーは、低域に集中すべきです。そうすれば中域は他の楽器の音とぶつかることはありません。
3. 「ボクシー」

低域も高域も不十分で、ほとんど中域の周波数で構成される音やミックスのことです。
例: 「このギターはボクシーな感じだね。もっとハイが録れるマイクを使った方がいいかな。」
「このギターはボクシーな感じだね。もっとハイが録れるマイクを使った方がいいかな。」
ボクシーなミックスサウンドはフラットで、詳細が欠けているものです。
自分のミックスを、他の参考音源と比較してみると、その理由が見えてきます。
解決方法:
中域を過度に上げ過ぎず、周波数スペクトラム上で極端に突出している部分に注意して、ボクシー感を回避しましょう。
4. 「ウォーム」(暖かみ)

「ウォーム」(暖かみ)は一般的に、ハーモニック(高調波)ディストーションがかかり、高域が過度に誇張されていないような状態を指します。
例: 「おお、チューブコンプレッサーのプラグインを追加すると、ボーカルがウォームな(暖かい)感じになるね」
「ウォーム」(暖かみ)は、アナログ機器によって生み出されるクオリティーでとても人気があります。ミックスを自然に、豊かに、楽しめるように仕上げてくれます。
「おお、チューブコンプレッサーのプラグインを追加すると、ボーカルがウォーム(暖かい)な感じになるね」
この効果を得るには:
サチュレーションなどのアナログスタイルのプロセッサーを使って、徐々に高域を追加して、ウォーム感を作ります。
でも控えめに行うようにしてください。アナログエミュレーションプラグインによる過度な人工的サチュレーションは、逆に荒々しくなりすぎることがあります。やり過ぎには注意しましょう。
5. 「ハーシュ」(耳障り)

「ハーシュ」(耳障り)とは、過大な中高域レンジを表し、リスナーの耳を疲れさせてしまいます。.
例: 「シンセの矩形波が結構ハーシュ(耳障り)だな。フィルターのカットオフを少し下げてみてくれる?」
「ハーシュ」(耳障り)は多くのミックスで見られるメジャーな問題です。リスナーの耳を疲れさせる事は避けなければなりません。
ハーシュなミックスは、イヤホンやラップトップスピーカーのような一般的なリスニングシステムをさらに悪化させます。
解決方法:
3~5kHzレンジを扱う際、EQやマイクのポジショニングなどで十分注意してハーシュな音を回避します。
6. 「デプス」(深み)

「ルームマイクのパンを広げると、ドラムにデプス(深み)を与えます。」
「デプス(深み)」はミックスに3次元クオリティーをもたらします。
例:「ルームマイクのパンを広げると、ドラムにデプス(深み)を与えます。」
「デプス」(深み)は、リスナーを楽曲の世界に引き込み没頭させます。
楽器の分離感や、全体の空間感覚を作るのを補助します。
効果を得るには:
録音の際に、近いマイクと遠いマイクを組み合わせることで、ミックスの中に様々なアンビエンスを混ぜることが出来ます。
異なる距離感やパンポジションを持つ様々な音源は、ミックスにデプス(深み)を付加します。
7. 「エアー」

「エアー」は、ミックス内の高周波数帯にある、かすかなライブ感のことです。
例: 「そのオーバーヘッドのリボンマイクは結構暗めな感じだから、ちょっとエアーを足したほうが良いかな。」
「エアー」は、ボーカルやルームマイクのような音源に、リアル感や3次元感をもたらします。滑らかで、オープンで、空気感のある高周波帯域は、多くのミックスが目指すところです。
「そのオーバーヘッドのリボンマイクは結構暗めな感じだから、ちょっとエアーを足したほうが良いかな。」
存在感があり、心地良く、EQで丁寧に調整された高周波数帯域にしっかり配慮しましょう。
効果を得るには:
スムーズな響きのEQに穏やかなベル型またはシェルビング型フィルターを適用し、8〜16 kHzのどこかでトップエンドを軽くブーストします。
でも注意してください。やりすぎは「ハーシュ」なトラックを作ってしまいます。少しずつ調整していくのがコツです。
ミックスの繊細な「エアー」はボーカルをスムーズに目立たせ、ルームマイクの録音を生き生きとリアルな感じにしてくれます。
ミックスについて話す時、何を話すのか
ミキシングはとても主観的な作業です。説明するときに使う用語もやはり主観的です。
それぞれのエンジニアは「エアー」や「デプス」といった言葉を別な意味で捉えているかもしれません。
これらの用語の定義は、ミックスの問題点や強み、特定の音に近づける方法などについて考え、伝えるためのガイドラインに過ぎません。
さあ、これらの意味が理解できたら、ミックスを頭の中のイメージにさらに近づけてみましょう!
LANDRブログの投稿を見逃すことはありません